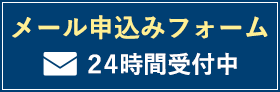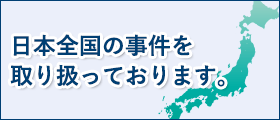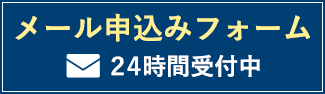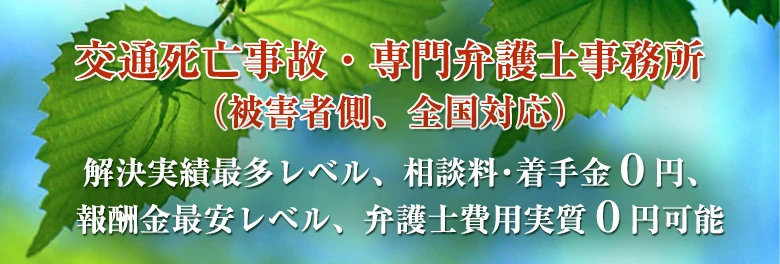
交通事故の死亡事案で、葬儀関係費用が認められる範囲の解説
1 葬儀関係費用~結論
(1)
葬儀関係費用は、裁判・弁護士基準では、原則として、150万円が認められています。
但し、実際に支出した額が、これを下回る場合、実際に支出した額が認められています。
この点、「葬儀関係費用」には、「葬儀費用」のみならず、その後の法要(四十九日法要等)・供養等を執り行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等も含まれるとされています。
ただ、「葬儀関係費用」の上限額は、原則として150万円とされています。
(2)
また、香典については、損益相殺(不法行為等で損害を被った者が、同じ原因で利益を得た場合、損害額から利益分を控除すべきであるという原則)を行いません。
ただ、逆に、香典返しは、損害と認められていません。
また、遺体運送費は、葬儀関係費用とは別に、基本、損害と認められています。
2 葬儀関係費用の裁判・弁護士基準について
(1)裁判・弁護士基準
上記1は、裁判・弁護士基準になります。
裁判・弁護士基準は、裁判所が基本的に認めている基準になります。
裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、損害の定型化・定額化の方針を打ち出しており、裁判所の提言や判例の傾向をもとに、裁判・弁護士基準が存在します。
(2)赤い本基準、青本基準
裁判・弁護士基準は、基本的に、
- 通称「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部))の基準
- 通称「青本」(「交通事故損害賠償額算定基準─実務運用と解説─」(日弁連交通事故相談センター))の基準
になります。
この点、「赤い本基準」は、東京地裁基準、「青本基準」は、全国基準とされています。
ただ、現在、「赤い本基準」が、実務で最も使われている裁判・弁護士基準になります。
(3)弁護士に依頼した場合に基本的に獲得可能
被害者遺族は、弁護士に依頼すれば、裁判・弁護士基準の金額を基本的に獲得できます。
当事務所(交通死亡事故・専門弁護士事務所)へのご相談・ご依頼をお勧めいたします。
3 葬儀関係費用の参考文献・判例
(1)赤い本
葬儀費用は、原則として、150万円。
但し、これを下回る場合は、実際に支出した額。
香典については、損益相殺を行わず、香典返しは、損害と認めない。
(2)「別冊判例タイムズ38」における、東京地裁基準
葬儀費(仏壇、仏具購入及び墓碑建立費を含む。)については、社会通念上必要かつ相当と認められる限度において、損害賠償を請求し得る。
東京地裁交通部においては、葬儀費用については、原則としておおむね150万円を上限として、これを認めることとしている。
(3)「交通損害関係訴訟」における、東京地裁基準
一般に、葬儀(訪問客の接待、遺体の処置を含む。)やその後の法要(四十九日、百日の法要等)・供養等を執り行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等の葬儀費用等については、社会通念上相当と認められる限度において、不法行為により通常生ずべき損害として、その賠償を請求することができるものとされている。
香典については、損益相殺をせず、香典返しは、損害として認めていない。
いわゆる赤い本では、原則として150万円とし、現実の支出がこれを下回る場合には、実際に支出した金額の範囲において、賠償を認めるとしている。
遺体搬送料等の費用については、葬儀等とは直接には関係がない費用であるから、葬儀費用等とは別に、積極損害として認められる。
(4)青本
葬祭費の基準は、130万円~170万円。
香典返しの費用は、損害とはされない。
遺体運搬費は、葬儀費用とは別途損害算定をすべきであろう。
(5)大阪地裁基準
葬儀関係費の基準額は、150万円。
葬儀関係費は、原則として、墓碑建立費・仏壇費・仏具購入費・遺体処置費等の諸経費を含むものとして考え、特段の事情がない限り、基準額に加えて、これらの費用を損害として認める扱いはしない。
遺体運送料を要した場合は、相当額を加算する。
香典については、損害から差し引かず、香典返し、弔問客接待費等は、損害と認めない。
(6)最高裁昭和44年2月28日判決
遺族が、墓碑建設、仏壇購入のため費用を支出した場合には、その支出が社会通念上相当と認められる限度において、不法行為により通常生ずべき損害として、その賠償を加害者に対して請求することができるものと解するのが相当である。